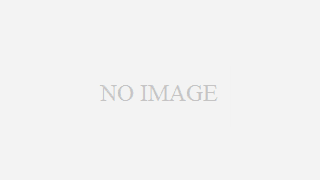私の会社の決算は8月末です。なぜそうなったのかは解りませんが、昔からそうだったので、いまだにそうしています。決算と言っても、伝票やら書類を整理し、在庫を集計し、税理士に報告。これだけです。
中小企業とは言え、可能であれば税理士を雇っておいた方が良いでしょう。税理士にお願いすると費用はかかりますが、安心や効率という意味で大きな価値があります。もちろん「自分でやれる部分は自分でやった方がいい」とお考えの方もいらっしゃると思います。最近は会計ソフトも進化しており、簿記の基礎知識があればかなりのことを自分で進められるようです。では実際の仕事の流れを交えながら、税理士を雇う意味を整理してみましょう。
1. 経営者がやるべき基礎的な作業
最初の段階で大切なのは「日々の取引を記録する」ことです。
例えば、売上・仕入・経費のレシートや領収書を集め、伝票に落とし込む。この作業を最初は紙の振替伝票でやってみると、借方・貸方の仕組みが体に入りやすくなります。
慣れてきたら、会計ソフトに入力して管理していくのが効率的です。ソフトを使えば集計や月次試算表も簡単に出せます。
さらに経費関係は、レシートをまとめて税理士に送るのが一般的な流れです。最近ではクラウド型のサービスを通してレシート画像を共有したり、スマホで撮って送るだけで処理してもらえる方法もあるようです。
つまり経営者の役割は、
- レシートを失くさず集める
- 伝票に記入・入力する
- 必要なデータを税理士に送る
といった「日常的な記録と整理」が中心になります。
2. 税理士が担う仕事の流れ
経営者が集めたレシートや入力データをもとに、税理士は次のような仕事をします。
- 入力の誤りや抜けがないかチェック
- 法律に沿った処理に修正
- 節税につながるアドバイス
- 決算書や税務申告書の作成
税理士の強みは、法律に基づいて正確に処理できる点です。経営者が簿記を理解していても、最新の税法や特例までは追いきれません。そこを税理士が補ってくれるのです。
3. 経営者のスキルと税理士の役割の分担
経営者本人も会計の知識を持っていた方が絶対良いと言えます。。少なくとも「(日商簿記)簿記3級」くらいは早めに取っておくと、仕訳や決算の仕組みを理解でき、税理士との会話もより深く理解できます。弊社は商業系企業なので「3級」ですが、工業系の方は「2級」まで押さえておきたいものです。
簿記の知識があれば、数字の意味を理解し、自分で経営判断に活かすことができます。逆に知識がなければ「税理士任せ」になり、本来得られるアドバイスも活かせません。
大事な事は「どこまで自分でやり、どこから税理士に任せるか」をはっきりさせることです。例えば_税理士への顧問料が心配な方は伝票の入力までは自社でやり、チェックと申告は税理士に任せる。そうすればコストを抑えながら安心も得られます。
4. 合う税理士と合わない税理士
税理士にも色々なタイプがあります。
- 記帳や申告だけを淡々とこなすタイプ
- 経営の相談に乗り、資金繰りや融資のアドバイスをしてくれるタイプ
経営者にとって重要なのは、自分に合う税理士を選ぶことです。経営状況を理解してくれる税理士と出会えれば、心強いパートナーになります。逆に、話がかみ合わなかったり、相談しづらい税理士だと「ただの申告代行」にとどまってしまいます。
契約した税理士が合わないと感じたら、乗り換えるのも一つの選択肢です。会社の将来を左右する数字を任せる相手ですから、遠慮なく「信頼できる人」を選ぶべきです。